わくわく授業のアイデア
このコーナーでは、生徒の意欲を高めるために先生方が授業のなかで工夫しているちょっとしたコツを紹介します。
|
| 作文嫌いをなくす国語の授業のコツ |
| 10分で400字、テーマは○○。これで、「さあ作文を書け」と言われれば、大人でも戸惑う。だが、大石先生は、作文指導にちょっとした工夫をし、年間で100本にものぼる短文を作らせる。それを通して、子どもたちの作文嫌いをなくし、確実に文章表現能力を身につけさせている。 |
適切な手順で書けるよう、「道しるべの言葉」をあらかじめ用意。
書き切らせることで次へとつなぐ |
通年100本の短文を作らせる大石先生の指導は、いわゆるスパルタや単純な反復訓練ではけっしてない。
「基本的には、授業時間のなかの10~20分を使います。とにかく最後まで書き上げさせることが大事。出来、不出来は問題にしない。7~8行で終わってもいい」
その最後まで書き上げるという指導のために、大石先生はユニークな手法をとっている。それが、あらかじめ作文の段落を想定して、それぞれの書き出しの語を提示しておくというものだ。 |
| コツ1 テーマや難易度に合わせ、「書き出し言葉」や「つなぎ言葉」を提示、最後までリードする |
|
大石先生によると、作文が苦手という子どもは、大きく二つに分かれる。
(1)書く内容を見つけにくいというタイプ
(2)書き方がわからないというタイプ
だ。運動会、遠足など行事がテーマの、いわゆる生活作文で顕著に分かれるという。行事はポピュラーな作文指導のテーマだが、じつは子どもにとっては体験した情報量が多すぎ、内容を絞り込めないのだそうだ。
(1)の場合、指導は比較的簡単。「最も楽しかったことやつらかったことを書いて」と絞り込ませればいい。
問題は後者。書き方がわからないという児童だ。
「表や絵解きで、序・本・結など構成だけ見せても、実感させにくい」。これは、ものを大局から見る力が育っていないからといえる。1文字、1行は書ける、だがスタートからゴールまで、作業の全体像や奥行がイメージできないのだ。
「だからテーマに合わせ、『まず』『次に』『それから』『最後に』等、使用頻度の高い接続のための言葉を順番に並べて、この順に書けばいいんだよと教える」
これが、いわば「道しるべ語」だ。この手法は低学年からの指導も可能。学年が進むにつれテーマや達成度の水準が上がっていくので、道しるべの言葉を変化させて対応するのだという。
私たちも日常会話のなかで感情が高まり、言葉が出ないときがある。そのとき上手に「合いの手」を入れられると話し続けてしまうものだ。大石先生の指導は、そうしたテクニックに近い。 |
| コツ2 子どもが説明したいこと、説明できることをつねに意識し、そこから、次のテーマを見つけさせる |
|
大石先生が最初に「道しるべ語」を利用する指導を始めたのは、5年生の担任になったときだという。
「従来の作文指導では、説明的な教材が少なかった。感想を聞かせてくださいではなく、何々について説明してくださいというほうが、子どもには書く内容を認識させやすいと感じた」。それで一例として、以下のようにリードしたという。
テーマは「図工で習った『はし置き』の作り方を書け」。大石先生のクラスは全員、図工ではし置きの作り方を習っている。しかし隣のクラスはまだだ。子どもたちには「隣のクラスの友だちに、作文で教えてあげて」と言う。責任は重大だ。自らが教わったことを、きちんと説明しなくてはならない。はし置き自体は簡単な紙細工の域を出ないものだが、子どもは真剣になる。この場合も前述の『道しるべ』の言葉を用意しておく(表1)。 |
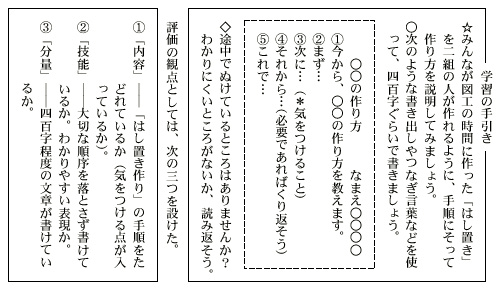
| ▲表1 順序をたどり説明するための学習の手引きと評価観点 |
|
「おもしろいもので、『紙を水に濡らす時間は何秒で、それ以上だと紙が破れやすくなって』など、注意点をていねいに書き込む子もいるんです。性格なんでしょうね」と大石先生。
「道しるべの言葉」を用意することで、芸才を封じる画一的な指導になりかねないか、との危惧は、的外れのようだ。むしろこのように、子どもの個性に気づく瞬間のほうがはるかに多いという。 |
| コツ3 作文をコミュニケーションツールとして位置づけ、書く楽しさを教える |
|
大石先生は、1年を通して、この「何々を説明させる」という手法の応用で授業を展開していった。例えば、「釣り」や「料理」など、子どもが興味を持っている対象について説明させるのだ。あるとき、作文は苦手だが釣りは得意だという子どもが、「見えているバス(ブラックバス)の釣り方」と題した作文を提出してきた。「では、見えていないバス(魚影のない状態)の釣り方はわかる?」と大石先生が問うと「それもわかる」と言う。「ではそれも教えて」…と連鎖させていく。クラスの釣り仲間同士で、作文を使って漁法を比較させるのもいい。後ろの黒板に貼り出して、子ども同士で教え合いもする。これは料理の場合も同様。「いずれレシピ集にしよう」と声が出るほど、作文の完成度は高まっていくという。いわば学級内パブリッシング。書くことは伝えることで、楽しいことなんだと教えていく。
「そのうえで、ディベートのまねごとにも発展させます」
例えば春と秋、海と山。どちらが好きか? と問いかけ、その理由を作文で説明させる。比較や評価という概念を文章で表現させるのだ。そこから対論や反論という深まりも生まれる。その次は仮定。「もしも何々がなかったら」という問いかけで、何々の部分は自由。それがなかった場合うれしいのか悲しいのか、その理由はなぜかを説明させるのだ(表2)。 |
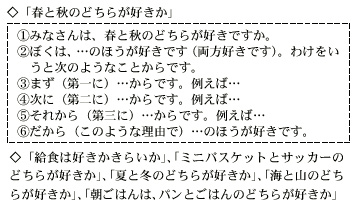
|
ここで出来上がった作文は、最も子どもの能力に飛躍を生む教材になる。ときには道しるべに、対論や仮定の言葉も混ぜておく。
他の授業で出てくる用語、例えば社会科の「伝統工芸」などという用語も、調べて作文で説明させるようにする。宿題に盛り込むこともあり、その結果が年間100本という数字になったのだという。
「話し言葉にも変化が出てきます。『総合的な学習の時間』の研究発表などで、すらすら論理的に説明したり…」
ギリシア時代、「言語」と「論理」は同一語だった。大石先生の作文指導はそうした思想に貫かれている。 |