 |
|
 |
|
Q6:評価はどのような流れで行うのでしょうか
A6:パフォーマンス評価は「ルーブリック」という表を作成して行います(図2)
ルーブリックは、横軸を「観点」、縦軸を「レベル」として、観点ごとにレベルが一目でわかる評価基準表です。これを用いることにより、複数の教師で評価基準を共有できます。評価の流れは以下の通りです。
- 事前に予想される解法をリストアップしておく(子どもの思考が見えやすくなる)。
- 複数の教師(できれば3人くらい)で採点し、得点やその理由をつき合わせる。
- 採点と並行して、ルーブリックの各レベルの状態を埋めていく。ある程度、採点を進めるとルーブリックがほぼでき上がるので、それを基に採点を続ける。新しい考え方が見られた場合、ルーブリックに追加する。
|
 |
図2 ルーブリック(「JELS」小6算数の一部抜粋) |
 |
▼クリックすると拡大します
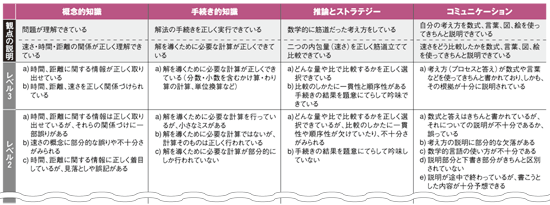
| 実際の表は、レベルが3~0の4段階になっている。「JELS」の調査では、「計算はできるが、意味がわかっていない、などの学力の偏り」や「筋道だてて考えたり、わかりや
すく伝えたりすること」を見る目的でこの4つの観点になった |
|
 |
|
Q7:評価の際に気を付けるべき点を教えてください
A7:採点が目的ではなく、一人ひとりの思考過程を見ることが大切です
採点にこだわりすぎると、パフォーマンス評価のよさが失われてしまいます。例えば、同じ得点でも解答の内容は異なりますから、単純な得点の比較に意味はありません。各観点の得点を合計すると、どの観点が弱いのかが見えにくくなるので、注意してください。
|
 |
|
Q8:学校現場でも取り入れられるのでしょうか。ポイントはありますか
A8:学校での実施は、子どもたちの経験を踏まえたパフォーマンス課題がつくれるというメリットがあります
小学校でパフォーマンス評価を行う際には、次のポイントを意識しましょう。
- ルーブリックは「A・B・Bに達していない」の3段階にするなど簡略化してもよい。
- 担任1人ではなく、学年団などのグループで取り組む。メンバーに該当教科に詳しい教師がいるとなおよい。
- 評価のみを目的とせず、「子どもの思考過程を理解できる」「教師の協同関係ができる」「教材や指導法の研究に役立つ」など、多様な利点があることに目を向ける。
- 課題やルーブリックはその後も利用できるので、経年で研究を続ける視点を持つ。
パフォーマンス評価は手間がかかりますが、子どもにとっても教師にとっても、実りの大きい評価法です。学んだ知識を複数組み合わせて使う課題をつくれば、1学期に1回行うだけでも有効だと思います。是非、取り組んでみてはいかがでしょうか。 |
 |
図1、2出典:『JELS~青少年期から成人期への移行についての追跡的研究~』(JELS:Japan Education Longitudinal Study)。
お茶の水女子大21世紀COEプログラム「誕生から死までの人間発達科学」におけるプロジェクトの1つ。松下教授は算数・数学学力調査のグループリーダーとして参加 |
 |
|