 |
|
|
 |
| まとめ :変わるもの・変わらないもの
|
 |
| 学校が「楽しい場所」であり続けるために |
 |
|
30年に渡る中学校の変化について、いくつかのデータを基に検討してきた。生徒も、教師も、その意識や行動は時代ごとの社会環境や教育政策の影響を受けて、さまざまに変わってきたことがわかる。その時々で学校や教師に何が求められるかに対応して、指導のあり方は異なるのだろう。
しかし、変わらないもの・変えてはいけないものもあると思う。教師は、生徒が学校での学びに意味を見出し、学校に楽しく通えるようにする努力を怠ってはならない。幸いなことに、そうした学校の価値は、この30年で大きく変わっていないかもしれない。
|
 |
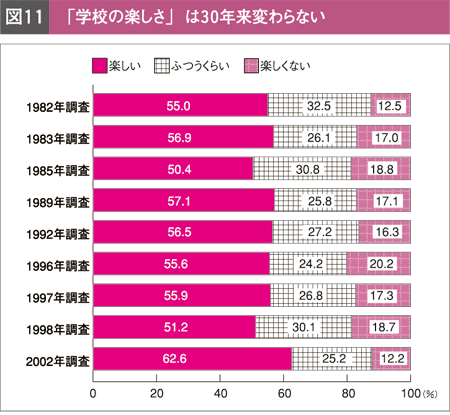
注1:1982年調査は『モノグラフ・中学生の世界』Vol.12(中学生の自己像~スモール・イズ・ビューティフル)、1983年調査は『モノグラフ・中学生の世界』Vol.15(学業成績~生徒たちは成績の良し悪しをどうとらえているか)、1985年調査は『モノグラフ・中学生の世界』Vol.23(中学生のえがく教師像~生徒たちは教師をどう評価しているか)、1989年調査は『モノグラフ・中学生の世界』Vol.33(学業成績の意味)、1992年調査は『モノグラフ・中学生の世界』Vol.43(疲れている中学生)、1996年調査は『モノグラフ・中学生の世界』Vol.54(「規範感覚」と「いじめ」)、1997年調査は『モノグラフ・中学生の世界』Vol.57(学校内の人間関係)、1998年調査は『モノグラフ・中学生の世界』Vol.60(都市の中学生・山村の中学生~地域差や学校差を考える)、2002年調査は『モノグラフ・中学生の世界』Vol.75(東京の中学生・ソウルの中学生~「のんびり」と「疲れ」の対比)。
注2:いずれの調査も、「楽しい」は「とても楽しい」「かなり楽しい」「やや楽しい」の合計、「楽しくない」は「ぜんぜん楽しくない」「あまり楽しくない」「やや楽しくない」の合計の比率を示している。 |
|
 |
|
図11は、生徒に学校が楽しいかどうかを尋ねた結果だ。これを見ると、多少の違いはあるものの、すべての調査年で5割を超える生徒が「楽しい」と回答し、「楽しくない」という回答は2割かそれ以下である。
今回は触れられなかったが、この間には学校の「荒れ」が問題になった時代もあった。それにもかかわらず、生徒はおおむね学校を「楽しい場所」と捉えていたようである。そこには、教師のたゆまぬ努力があったと推察する。
もちろん、「楽しい」を増やし、「楽しくない」を減らすよう力を尽くすことは、今後も続けていかなければならない。そうした変えてはいけないものを大切にしながら、いかに変わっていく環境に対応するかが、これからの学校、そして教師に求められるのだろう。
|
 |
|
 |
|