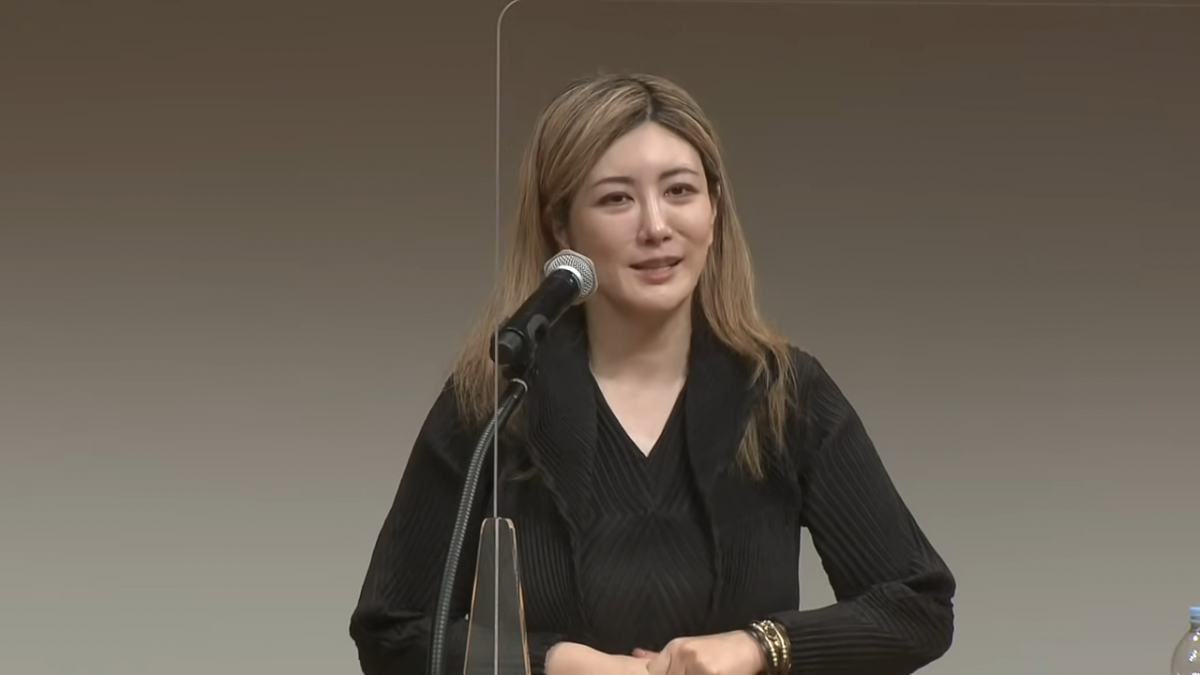前回は私の小学生時代から青年期までを振り返りながら、私が脳科学を研究するに至った経緯や、高校、大学での進路選択についての私見をお話ししました。今回は現在進行形で研究しているアートと脳の働きの関係と、教育や社会に対してアートが持つ大きな可能性について、お話ししたいと思います。
ホモ・サピエンスが生き残った理由は美の認知力にあった?
人間の脳の形状は他の動物と異なり、前頭葉という頭の前の部分が膨らんでいます。前頭葉は意思を決定すること、注意を振り向けること、計画を立てること、社会性などの処理に使われます。また、前頭葉は美の認知にも使われます。人間の脳は生物学的に見て、無駄な機能を持つ余裕はなく、出力レベルを抑える余地がないことも明らかになっています。解剖学的にも、これ以上脳が大きく進化すると、頭蓋を支える骨盤の構造に負担がかかり、進化が制約される可能性があります。そうしたぎりぎりのスペックですから、脳の重要な部分である前頭葉に無駄な働きをしている部分があるはずはありません。美を認知する機能は、意思決定や社会性などに匹敵する重要な役割を果たしているのではないかと考えています。
人間の進化の系統を見ると、ホモ・ハイデルベルゲンシス、ホモ・ハビリス、ホモ・ネアンデルターレンシスなどの複数から成るヒト属(ホモ属)の種の中で、人類(ホモ・サピエンス・サピエンス)以外はすべて絶滅しています。人類のゲノムの中に、わずかながら彼らの遺伝子の痕跡が見つかるのですが、種としては存続しておらず、我々は進化の観点では「孤立している」と言ってよい生物種です。我々は、なぜ「我々」だけなのでしょうか。これは、現在の私の東京藝術大学における研究テーマの根幹を成す軸の1つです。
人間が生き残った理由は諸説ありますが、解剖学的には、前頭葉の一部である前頭前野が他の種族よりも著しく進化したことが挙げられます。前頭前野は物事の美しさや憧れ、格好よさといった「美」を認知します。「美」を認知するということは、実用的ではなさそうな物事に対しても意味や価値を見いだすということです。これを象徴的価値と言います。例えば、ある遺跡では我々の地層からだけ食用ではない貝の化石が発見され、別のヒト属の地層からはそうした化石が見つからなかった、という報告があります。我々はその貝を何のために使っていたのか、用途は不明ですが「食べる」ためではなかったことは確かであり、象徴的価値を認めていた、と考えるのが自然です。その場での実利がなくても、別の場面や先のどこかで(交換などによる)メリットがある、と当時の人々は考えたのかもしれません。長期的な時間軸の認知と、象徴的価値の効果的な使用が可能になると、飢餓状態や大規模な戦闘行為を回避できる確率が高くなります。実際の遺跡では、人間の集落だけが長く存続していたと見られる形跡があるようなので、象徴的価値たる「美」の認知とは、一定数の人が信じているような富裕層の娯楽のようなものではなく、脳の副次的な機能でもなく、人間の存続そのものにかかわってきた、極めて重要な機能だと言えるのではないか、というのが私の仮説です。
現代アートの鑑賞とそれ以前のアートの鑑賞とでは、脳の中で使う領域が異なる
近代以前の美術には、誰が見ても美しく、写実的で、分かりやすい、文脈依存的でないといった特徴があります。そうした美術作品を見ている時は、前頭葉の中でも、目のくぼみのすぐ上にある、眼窩前頭皮質(がんかぜんとうひしつ)という部分が働いています。その部分で私たちは、食べ物をおいしいと感じたり、絶景を見て美しいと思ったりしているのです。
一方、現代アートは古典や近代美術と対比される芸術で、第二次世界大戦後以降の美術を指します。近代以前の美術の「分かりやすい」美しさと異なり、現代アートはいま一つ分かりにくいと感じる人が少なくないのではないでしょうか。その中には不快感を与えたり、見る人の感情を揺さぶったりするような作品もあります。そうした作品を目にした時、「自分は正直、この作品のよさが分からないけれども、有名な評論家が評価しているのだから、素晴らしい作品なのだろう」などと自分を納得させたり、戦争や災害に巻き込また当事者が制作した作品だから評価を高めたりするなど、文脈に依存する作品が多いことも現代アートの特徴の1つです。また、現代アートには、倫理観を揺さぶられる作品が多くあります。以上のような特徴を持つ作品を見ている時、私たちの脳の中では、誰もが美しいと感じる部分とは異なる部分が働いています。つまり、現代アートは、近代以前の美術を鑑賞する時とは異なる脳の部分に作用するのです。
有史以来、地球上に戦争がなかった時代は1割に満たないという試算があると、戦史の研究者から伺ったことがあります。自分は戦争など望んでいない、元来人間は十分に良識的であり、望んで戦争を始める人などほとんどいない、と多くの方は思っていらっしゃるかもしれませんが、家庭内の小さないがみ合いですら処理できず、苦労しているのが人間の実情です。経済的な非対称性(資源や権力、機会などの面での不平等)から搾取の構造ができてしまっていて、どちらかに不満が蓄積したり、相手の配慮が互いに当然のことになって、最初は良かったはずの関係が、いつの間にか修復不可能になってしまったりして、苦行のような生活を送っていらっしゃる方のほうが多いのではないか、とえます。たくさんのご相談を受けます。家庭内の平和のような小さな単位ですら、維持することが難しい。そんな生き物が、何十年も戦わずにいるというのは本当に大変なことなのです。
もっと言えば、個人ですら他者と平和に共存していくために努力が必要なのに、民族や国家といった集団になれば、平和の維持は困難の度合いを増すでしょう。相手に対して大規模な戦闘行為を起こさず、しかも自分側の不満も巧みに処理して、ともに栄えていられるというのは、奇跡に近いようなことなのです。少なくとも我が国にあっては、戦争のない幸せな時代を生きる僥倖(ぎょうこう・偶然に得る幸運)を改めて噛み締めてほしいと思いますし、できるだけ平和を長く維持する努力を国民一人ひとりが続けられることを祈るような気持ちでいます。
現代アートに触れる時、私たちが認知できる範囲は日常生活における水準から大きく拡張し、時空間と集団のサイズは、ともに広がっていきます。目の前の対立構造を制するより、長期的ないしは、より大規模な集団における互恵関係を維持する方が利益を最大化するためには都合がよい。配慮範囲の軸を大きくした時、究極の利己は、利他的であることと一致するのです。この視点を、何万回も繰り返し語られてクリシェ化した倫理観として上から押し付けるのではなく、自然な形で人々の内的な気づきとしてもたらすことに寄与できるのは、現代においてはもはやアートしかないのではないか、と私は考えています。
すべての美術作品に幼少期から触れることはお勧めしない
脳の様々な領域を鍛えておこうと、幼少期から様々な美術・芸術に触れさせようと考える保護者がいます。それ自体は悪いことではありませんが、美術作品の中には、触れたことで大きなショックを受ける作品や、ある程度成長してからでないと作品の内容を理解することができないものもあります。例えば、社会性や国家観を問う作家トルストイの代表作「アンナ・カレーニナ」などは、小学生には理解しにくいと思います。社会性がある程度発達してからでないと、作品の趣旨を分かろうとすることに力を注ぐあまり、「こんな難しい作品を理解している自分はすごい」などと、ゆがんだ承認欲求を育ててしまう恐れもあります。美術との出合いには適切な年齢があると私は考えています。教師や保護者は、美術作品の特徴と子どもの発達状況に大きな乖離がないかを確認した上で、子どもに作品を鑑賞させることをお勧めします。
子どもの脳を「トリミング」しないでほしい
学校教育においてお勧めしたい美術の鑑賞法があります。VTS(ビジュアル・シンキング・ストラテジー、Visual Thinking Strategies)をご存じでしょうか。それは、アートを通じて鑑賞者(学習者)の観察力、批判的思考力、コミュニケーション力を育成する教育方法で、簡単に言うと、作品の意味や制作意図、作者などについては伝えずに、教師や他の鑑賞者との対話を通してグループで作品を鑑賞する方法です。「この作品は有名な○○美術館に収蔵されている」「その作品は歴史的に重要で、高い価値があって評価されている」といったことは、単なる知識に過ぎません。その作品を見た人自身がどう感じ、考えたかが重要なのです。
VTSのメリットは数多くありますが、個を尊重し合うことの大切さと、そのために必要な心持ちやスキルを学べる点が特に素晴らしいと考えています。子どもは学齢が低いほど自由に考え、思ったことを率直に口に出します。大人はそうした自由な思考を持ちにくいですから、子どもに対して戸惑ったり、反論したくなったりするかもしれません。しかし、子どもがどんな反応を示しても、否定してはいけません。「あなたの意見はどのようなものであろうとも、まずは受け止められる」ことを伝え、心理的安全性を確保することが最も重要だからです。
そして、「とっぴなこと」を言う子どもに対しても、教師は動じないでもらいたいと思います。それは、教師が過ごしている大人の日常生活から見たら「とっぴなこと」かもしれませんが、子どもにとっては真摯な、大切な思いの反映かもしれないからです。大人自身も、子どもの頃に大人のステレオタイプを押しつけられ、思ったことを話したら否定された経験があると思います。そうした大人の言動がなかったら、好奇心の芽が枯れることはなく、大人に一生懸命話しても無駄だとは思わなかったのではないでしょうか。大人の価値観で子どもの脳を「トリミング」する、すなわち子どもの思考を制限するようなことはせずに、長期的な視点に立ち、子どもに「自分は認められている」と思える経験を積ませることで、子ども自身の力で非認知能力を伸ばすことを支援してほしいと思います。それができるかどうかが今、私たち大人に問われているのではないでしょうか。
(本記事の執筆者:神田 有希子)