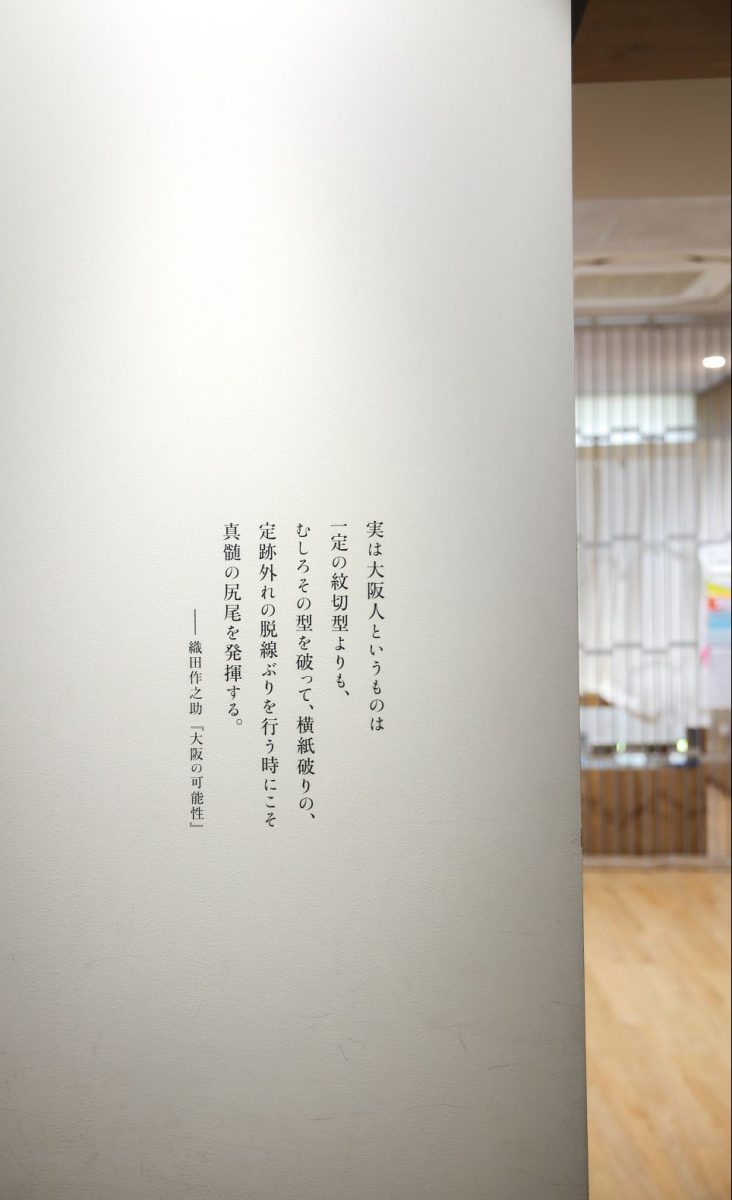少子化や教師不足、働き方改革など、様々な課題が学校を取り巻く中、学校経営者はどのような考えの下、経営にあたっているのかを尋ねる本コーナー。1回目となる今回は、学校法人大阪国際学園の奥田吾朗(おくだ・ごろう)理事長、大阪国際中学校高校の八谷芳樹(やつや・よしき)名誉校長、清水 隆(しみず・たかし)校長の3人に話を聞いた。2022年4月に開校した大阪国際中学校高校は、前身となる学校の創立以来、90余年の歴史の中で醸成してきた「全人教育」の精神を土台に、予測困難な時代を生き抜く力を育むための教育を追求している。

学校法人大阪国際学園 理事長
奥田吾朗(おくだ・ごろう)

大阪国際中学校高校 名誉校長
八谷芳樹(やつや・よしき)

大阪国際中学校高校 校長
清水 隆(しみず・たかし)
学校概要
大阪国際滝井高校と大阪国際大和田中学校高校が発展的に統合する形で2022年4月に開校。「全人教育」を基礎として、礼節を重んじ、世界に通じる心豊かな人間を育成している。
開校:2022(令和4)年
生徒数:1学年 中学校約95人、高校約345人
教師数:約90人
2024年度卒業生進路実績:国公立大は、東京大、大阪大、神戸大などに65人が合格。私立大は、早稲田大2人、同志社大、立命館大、関西大、関西学院大、以上4大学延べ259人を含む、延べ921人が合格。
創立以来の建学の精神を、戦略的思考で具現化
奥田 大阪国際学園は1929年に誕生しました。当時の学校要覧では、「本校教育の眼目」として「人間を作る教育」が提唱されています。92年には、創立時から受け継がれた「人間を作る教育」という学園のあり方を、「全人教育」という言葉でグループ共通の建学の精神として掲げました。そして2022年の大阪国際中学校高校の開校にあたり、校訓を「人間をみがく」にすることで、建学の精神である「全人教育」を、さらに明確化しました。
校訓「人間をみがく」を中学校と高校の教育活動に反映させるための戦略計画が、八谷芳樹名誉校長とともに立案した「基本戦略プラン【VISION100】」(以下、基本戦略プラン)です(図1)。それは、29年に迎える学園創立100周年に向けて、大阪国際中学校高校の特長を際立たせるための、教学と経営を一体化した学校経営のためのマップとも言えるものです。
八谷 私は公立高校に教員、そして管理職として長く勤めてきましたが、その中で、組織というものは、よくも悪くもトップのマネジメント次第で大きく変わることを実感してきました。公立高校を退職後は大学に移り、戦略マネジメントを研究しました。そこでは、名古屋大学総長補佐や名城大学副学長・理事などを歴任した池田輝政先生から、教学と経営をつなぐ中長期的な「戦略プラン」の作成について学びました。戦略プランは、企業が経営環境を分析し、経営理念を実現するための論理的な道筋を表現する戦略的思考法(strategic thinking)に基づいて作成されます。私たち教師は、教育の世界とビジネスの世界を切り離して考えがちですが、既存の価値観にとらわれず、企業の組織経営の手法を学校経営に落とし込むことで、トップの「志」が浸透する学校をつくることができると考えました。
奥田 「基本戦略プラン」では、ミッションステートメントとしての校訓「人間をみがく」(写真1)を新たに掲げることで、ミッション「礼節を重んじ、世界に通じる心豊かな人間を育成する(GLOBAL MINDを醸成する)」を再確認するとともに、生徒を主語にしたビジョン「自分らしく生き抜く力を身につけ、未来社会の担い手となる」で主体性を強調しています。そして、ビジョンの実現のために学校に求められることを、学校を主語にした3つのバリューで整理しています。ビジョン、ミッション、バリューなどをどのような言葉で表現するのか、八谷名誉校長とともに練り上げていく中で、私は改めて教育の本質について考えることができました。私は理想像から物事を語りがちなのですが、八谷名誉校長から全国の学校の実情や初等中等教育の課題を聞き、これからの社会で必要とされる若者を育てるためにはどんな学校であるべきかを一緒に考える過程で、理想像に加え、現実と向き合い、取り組むべき教育活動の実像が少しずつ見えてきたように思います。
八谷 「基本戦略プラン」は、「生徒募集」「『学び』の特色」「戦略・組織の運営」の3つの戦略ドメインを基本の柱に構築されています。その考え方は、海外の大学経営などにも通じる、グローバルスタンダードなものです。その上で、「人間をみがく」を校訓に掲げる本校の教育を推進する際には徳育が必要不可欠なため、「『人間形成』教育の特色」を本校独自の戦略ドメインとして加えました。
「基本戦略プラン」は、学校経営者の志を1枚の地図として表現したものです。教職員がそれぞれの立場から、基本目標、行動目標、戦略計画の3層を追うことで、自分には何が求められているのか、それはなぜ求められているのかを、トップと対話するように理解することができます。トップの思いが伝わった暁には、指示を待たずに教職員一人ひとりが動き出すのです。
奥田 「基本戦略プラン」は、学園創立以来、本学園が大切にしてきた建学の精神を土台としています。その土台の上に何を足していけば、10代の若者の感性にフタをすることなく、変化の大きな社会を生き抜く力を育むことができるのか、八谷名誉校長とは繰り返し議論を交わしました。互いに熱が入り過ぎることも正直、何度かありましたが、「よい学校を次の時代に残したい」という思いが共有できていたからこそ、本気の議論を続けることができたのだと思います。
「基本戦略プラン」を基に進む学校づくり
清水 大阪国際中学校高校のミッション、ビジョン、そして具体的な行動指針となるバリューを「基本戦略プラン」において示しています。その中でも本校の教育活動の原点となる取り組みの1つが「立志式(写真2)」です。それは生徒一人ひとりが志を立て、それぞれの生き方の原点とするように宣言するもので、中学2年次と高校2年次に実施します。特に高校2年次の立志式では、これからの社会がどうあってほしいのか、自分はその実現に向けてどのように貢献したいのか、また、社会や自分をどう変えていきたいのか、生徒自身の人生設計として2,000字の論文で表現し、発表します。立志式は教科の枠を超え、本校の教育活動を貫く存在となっています。
八谷 生徒一人ひとりが本校の教育目標を十分に理解して学校生活を始められるよう、入学直後2週間にわたって、中学1年生と高校1年生を対象とした「スタートプログラム」を実施しています。理事長や校長などが建学の精神や校訓について語り、なぜ本校では立志式を行うのか、どのように学校生活を過ごしてほしいかなどを生徒に伝えます。また、学校生活の多くの時間を占める授業についても、各教科の学習が現代を生きる中学生・高校生になぜ必要なのかを説きます。一般的な入学者オリエンテーションとは一線を画す、本校独自のプログラムです。生徒たちが教育理念を十分に理解し、足並みをそろえて学校生活を始められるよう、できるだけ早く互いをよく知り、理解し合える内容にするように配慮しています。
清水 また、本校は22年3月に、高校卒業資格を取得することができる一条校では大阪府内唯一の、英語によるIBDP(国際バカロレア・ディプロマ・プログラム)の認証を取得しました。IBは、国際的な視野で行動するための能力やスキルを養う教育プログラムです。海外の大学へ進学し、国際社会で活躍する人材を育てるという目的は、本校の教育理念にも合致するものです。IBコースの開設時には、「基本戦略プラン」を基に、本校として世界に通じる人材をどのように育てていくのかを担当教師と話し合いました。
奥田 大阪国際中学校高校の開校にあたっては、戦略ドメインである「『学び』の特色」や「『人間形成』教育の特色」に沿った教育環境の整備にも力を入れました。 “Touch! Feel! Think!”をコンセプトに、キャンパスのすべてが学びの場となるようにデザインしました。4階建ての校舎棟の廊下や壁には、至る所に本棚を設け、校舎全体が図書館となるように設計しました(写真3)。また、本は、一般的な学校図書館の分類とは異なる、本校独自の5つのテーマ「世界へはばたく」「日本をさぐる」「自然にふれる」「社会をかける」「自分をみがく」ごとに配架されています。校内の各所に、文学や歌、哲学・思想、名言などから引用した「言葉のサイン」(写真4)を記し、図書の配架や実習教室と連動させることで、生徒の感性を刺激しています。
清水 たくさんの本棚の影響もあってか、本校は本に親しんでいる生徒がとても多く、約9割の中学生が、学校の図書館で本を借りた経験があります。また、約4割の中学生が、毎月図書館で本を借りています。子どもたちの「読書離れ」が社会問題になっている今、そうした学校は珍しいのではないでしょうか。オープンスクールに参加した小・中学生から、学校全体が図書館となっている、その雰囲気が気に入り、「この学校に行きたい」と入学を希望してもらえることも少なくありません。
よりよい学校づくりから、よりよい地域、国づくりへ
奥田 「基本戦略プラン」を推進していくために、今後は教職員の教育観を時代に合わせてバージョンアップしていくための研修の充実を図ることも考えています。私は28歳の時に本学園の理事長に就任しましたが、次の世代にどのようにバトンをつないでいくか、最近よく考えるようになりました。トップが変わるからといって、学校の伝統や建学の精神までもが変わることは許されません。教育の柱として何を残し、磨いていくか、一人ひとりの教職員に考えてもらう機会としても、研修は重要だと考えています。
八谷 研修の手法の1つとして、「基本戦略プラン」を使った振り返りが考えられます。特に、経営陣と生徒が「基本戦略プラン」を前に、同じステークホルダーとして、学びのこれまでとこれからを語り合うことはとても有意義だと思います。そのような取り組みを経て、「基本戦略プラン」そのものを、より生徒に合った形に見直すこともあるかもしれません。
清水 25年3月、大阪国際中学校高校の1期生が新しい進路を踏み出します。今後、卒業生が大学や社会で活躍する様子を、本校の教育力の証しとして広く発信していくことも必要です。建学の精神が卒業後、どのように発露されていくのかを知ることも、本校教師の教育力の向上につながると思います。
奥田 個性的な学校が全国にたくさんできれば、次代を切り拓く可能性を秘めた若者が、日本各地で生まれるはずです。私立、公立の区別なく、すべての学校がよりよくなっていくことが重要ですし、そのためには、学校同士が協働することも必要です。例えば、学校全体が図書館という本校のあり方は、「基本戦略プラン」の遂行に資するものですが、周辺の学校と協働して、本に親しむ地域づくりのための活動を展開することなども考えられます。次の時代に残すべきよい学校、よい地域を、学校経営者として考え続けていきたいと思っています。





-900x1200.png)